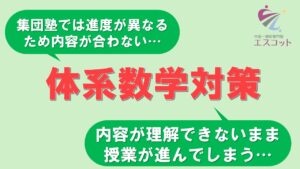
中高一貫校で広く採用されている『体系数学』は、公立中学校の教科書よりも量が多く、内容も高度になりやすい数学教材です。
分野ごとに内容が体系的にまとめられており、同じ分野を「やさしい問題 → 難しい問題」へと段階的に学べる一方で、授業進度が速く、自力での学習が難しいと感じる方も少なくありません。
このページでは、
- 『体系数学』とはどのような教材か(中学〜高校・各巻の位置づけ)
- 体系数学で多くの生徒がつまずく理由(レベル・難易度の感じ方)
- 体系数学を「負担」ではなく「武器」にするための攻略法(Level A/B/Cの使い方)
- 中高一貫校専門塾エスコットによる体系数学対策(1対1・オンライン対応)
を、やさしく整理して解説します。体系数学の特徴を理解し、効率よく学習を進めるための参考にしてください。
体系数学とは(まず結論:中高一貫校向けの体系的教材)
『体系数学』は、数研出版が発行する中高一貫校向け教科書で、特に上位校で採用されることが多いとされています。
同系列の分野が体系的・連続的に掲載されているため、学習の設計がしやすい反面、先取り前提で進む学校では負荷が上がりやすい教材でもあります。
- 同じ分野の内容を、簡単なものから難しいものへと体系的に学べる
- 先取りでカリキュラムが進むため、内容が高度になりやすい
- 参考書・問題集・書き込み式ノートなど、一式セットで使われることが多い
シリーズを通して中学〜高校範囲の数学を総合的に学べる教材ですが、学校の進度・先生の運用・課題量によって「体感の難しさ」が変わる点は押さえておくと安心です。
公立教科書と比べて「量・進度・難度」が上がりやすい理由
体系数学は分野ごとにまとまっているため、同じテーマを短期間で一気に進める運用になりやすい傾向があります。
その結果、理解が追いつかないまま次へ進んでしまったり、復習が後回しになったりすると、苦手が積み上がりやすくなります。
体系数学のレベル・難易度(ついていけない原因の整理)
体系数学は量が多く、内容も難しめに感じられることがあります。その分、理解が進めば大学受験対策にもつながる教材ですが、現場では次のような課題がよく見られます。
授業進度が速く、理解が追いつかない
中高一貫校の授業は先取りが基本のため、
- 内容が理解できないまま授業が進んでしまう
- 「なんとなく分かったつもり」の状態で、定着する前に次の単元へ進んでしまう
といったケースが起こりやすくなります。
量・難易度が高く、自力学習が難しい
- 学習すべき内容が多く、予習・復習にかなりの時間がかかる
- 内容そのものの難易度が高く、自力で学習を進めるのが難しい
授業中に理解できたつもりでも、復習の演習量が足りず、定着する前に抜けてしまうこともよくあります。
課題量が多く「こなすだけ」になりやすい
学校によっては、問題演習のほとんどが「課題」として課される場合もあります。その場合、
- 自力で問題演習をしようとしても相当な時間が必要
- とにかく課題を終わらせることが優先になり、内容理解が追いつかない
といった「やっているのに力がつかない」状態に陥りやすくなります。
体系的だからこそ、ひとつのつまずきが致命傷になりやすい
- ひとつつまずくと、その先の内容すべてが分からなくなりやすい
- 自力で遡ってフォローすることが難しく、苦手が雪だるま式に広がる
- 学年が上がったあとに「同じ分野を易しい問題から復習し直す」機会が少ない
- 定着しきれていない分野があっても気づきにくい
- 定期的に復習しないと、過去の内容を取り戻すチャンスが少ない
定期テスト・塾との進度のズレ
中高一貫校の定期テストは出題範囲が広く、体系数学に沿って応用問題も出題されることがあります。しかし、
- 高難易度のため、自力でのテスト対策が難しい
- 塾に通っていても、塾の進度と学校の進度が合わないことがある
- 集団授業の塾では、学校と同じように「分からなくても授業が進んでしまう」
といった負のループに入りやすいケースもあります。
・量が多く、問題をこなすことができない
・問題演習が十分にできない
・学習指導要領の範囲を超える難しい問題が多い
・集団塾では進度が異なるため内容が合わない
体系数学1〜5はどの学年で何を学ぶ(中学/高校の位置づけ)
体系数学は巻ごとに学年の目安があります。ただし、学校によって進度は異なるため、「自分の学校がどこまで進んでいるか」をまず確認すると整理しやすくなります。
体系数学1(中1・中2用)
体系数学1は、中1・中2生向けの教材で、代数分野・幾何分野の基礎を固めます。
正負の数/文字式/一次方程式/連立方程式/不等式/1次関数 など幾何分野:図形の基本的な性質を知る
平面図形/空間図形/合同と証明 など
体系数学2(中2・中3用)
体系数学2は、中2・中3生向けで、「中学内容の仕上げ」と「高校数学への橋渡し」を担う1冊です。
式の展開/因数分解/平方根/二次方程式/y=ax²/確率 など幾何分野:図形のいろいろな性質をさぐる
相似/線分の比(チェバ・メネラウスの定理)/円/三平方の定理 など
体系数学3(高1・高2用)
体系数学3は、高1・高2生向けで、内容は「数式・関数編」と「論理・確率編」に分かれています。
式と計算/3次式の展開/因数分解/恒等式/等式・不等式の証明/二次関数/三角比/集合/命題・証明/データの分析 など論理・確率編:論理・確率と統計・整数の性質
集合/順列・組み合わせ/確率/整数の性質/三角形の性質/円の性質/空間図形 など
体系数学4(高2用)
体系数学4は、主に高2生を対象とし、微積分の基礎と数列・ベクトルを扱います。
式の計算/複素数/2次方程式/高次方程式/恒等式/図形と方程式/三角関数/指数関数/対数関数/微分法/積分法/数列/平面ベクトル/空間ベクトル など
体系数学5(高3用)
体系数学5は、高3生向けで、複素数平面と微積分の応用を中心に学習します。
ロピタルの定理/微分方程式 など
「体系問題集」「書き込みノート」はどう使う(Level A/B/Cの回し方)
体系数学は、参考書・問題集・書き込み式ノートなどがセットで運用されることが多い教材です。
ただ、やみくもに全部を「消化」しようとすると時間が足りなくなりやすいので、まずはレベル(A/B/C)を基準に優先順位を決めると整理しやすくなります。
Level Aで土台 → Level Bで得点帯 → Level Cは目的に応じて
体系数学は、問題の難易度がLevel A/B/Cに分かれています。難易度は、A → B → Cの順に上がっていきます。
- Level A:教科書レベルの基本問題。まずはここで基礎を固める。
- Level B:幅広い種類の問題が揃った標準~やや難レベル。→ Level Bが理解できていれば、定期テストで上位に入れるレベルに近づきやすい。
- Level C・総合問題:難易度が高く、入試レベルの応用問題が中心。
学習の基本は、
- Level Aで基礎を固める
- Level Bで標準~応用レベルを徹底反復
- 必要に応じてLevel C・総合問題に挑戦
という流れです。
つまずいたときの戻り方(どこまで戻すかの決め方)
特にLevel Bについては、
- 解けなかった問題は、解けるようになるまで何度もやり直す
- 一度は解けた問題も、時間を置いて定期的に反復練習する
が重要です。やり直しの際は「どの知識が抜けていたか」を言語化し、必要ならLevel Aの類題まで戻る、という“戻り幅”を意識すると、再発が減りやすくなります。
体系数学とチャート式の違い(役割の違いと併用の考え方)
検索で「体系数学とチャート式の違い」が気になる方も多いかもしれません。
どちらが良い・悪いというより、教材の役割が少し異なると考えると整理しやすいです。
学校教材としての体系数学/受験参考書としてのチャート
- 体系数学:学校の進度に沿って学ぶ“教科書型”。分野がまとまっているため、学習設計はしやすい一方、進度が速いと負担が増えやすい。
- チャート式:受験を見据えた“参考書・問題集型”。体系数学の理解を補ったり、演習量を増やしたりする目的で使われることが多い。
学校の運用や本人の目標(定期テスト重視/受験も見据える等)によって、相性は変わります。
どちらを先にやるべきか(状況別の判断)
迷いやすいポイントですが、まずは学校の授業・定期テスト範囲(体系数学)を軸にして、理解が薄い箇所を補う形で参考書・問題集を追加する、という順番のほうが無理が出にくいことがあります。
ただし、学校の進度と合わない場合は、取り組む順序を調整した方が良いケースもあるため、状況に応じて検討すると安心です。
体系数学の採用校はどう調べる(よくある誤解の整理)
「体系数学の採用校」を知りたい場合、ネット上の断定的な一覧は根拠が不明なこともあるため、まずは自分の学校が何を使っているかを確実に確認するのが安全です。
学校配布物・シラバス・教科書案内での確認手順
- 新学期の教科書・教材配布プリント(購入リスト)を確認する
- シラバスや授業の進度表に教材名が記載されていないかを見る
- 学校指定の購入サイト・書店案内がある場合は、教材名を照合する
- 不明なときは、先生に「使用教材名」を確認する
「採用=難関校」とは限らない(判断の注意点)
体系数学は上位校で採用されることが多いと言われますが、採用の有無だけで学校の難易度を決めつけるのは難しい面があります。
重要なのは「どの巻をどのペースで進め、どこまで課題として出すか」です。採用の有無よりも、運用のされ方を見て学習計画を立てるほうが実用的です。
体系数学の攻略法(テストで点にする学習手順)
中高一貫校専門塾エスコット(Escot)では、完全1対1の個別指導で、上記のような課題に対して次のような対策を行っています。
反復の設計(週の復習ルーティン/テスト前の優先順位)
体系数学は、分からない問題をそのままにせず、理解 → 練習 → 反復のサイクルを回すことが大切です。
とくに課題が多い学校ほど、何を優先するか(A→B→必要に応じてC)を決めて進めると、学習が破綻しにくくなります。
エスコットの支援:板書プリント・データ管理・学年別コース・オンライン
当塾では、授業が終わるたびにその日の授業の板書をそのままプリントとしてお渡ししています。
- 授業中に解説した解き方・発想が、そのまま手元に残る
- 復習の際、「どうやって解いたか」をすぐに思い出せる
さらに、板書データはデータベースで管理しているため、
- 「一度は解けたのに、時間が経って解けなくなった問題」も、過去の板書をすぐに呼び出して復習できる
- 過去に受講した授業の復習・再演習を、タイムリーかつ効率良く行える
体系数学は、分からない問題をそのままにせず、きちんと理解し、反復練習することが何より重要です。そのための「仕組み作り」まで含めてサポートします。
学年別単元と開講コース
学年別の数学対策と扱う単元は、以下のリンク先で詳しくご案内しています。学年別にコースを設けており、学校の進度・理解度・目標に合わせた指導が可能です。
教室型の授業に加え、オンラインでも同様の授業が受講可能です。オンライン授業については、
コチラ
をご覧ください。
中高一貫校専門塾エスコット(Escot)は、完全1対1の個別指導で、生徒さん一人ひとりに合わせた体系数学対策を行っています。状況やお悩みはそれぞれ異なりますので、まずは一度ご相談ください。
数学の勉強方法を見直したい方へ
体系数学の内容に入る前に、そもそもの数学の勉強法を見直すことも大切です。
- 代数分野の勉強法は、数学(代数分野)が中々出来ない生徒さん向けの勉強法を参考にしてください。
- 数学全般が苦手に感じている場合は、コチラにあるように、学習方法を工夫するだけで状況が好転する可能性もあります。
普段の学習方法を見直しつつ、体系数学を活かして成績アップを目指していきましょう。
まとめ:体系数学を「負担」から「武器」に変える要点
本ページの内容を整理すると、体系数学を使いこなすためのポイントは次の通りです。
- 体系数学は、分野ごとに内容が体系的にまとまった中高一貫校向け教材で、公立教科書よりも量・難易度ともに高く感じられやすい
- 同じ分野を「やさしい問題 → 難しい問題」へと連続して学べる一方、ひとつのつまずきがその先の学習に大きく影響しやすい
- 授業進度の速さ・課題量の多さ・自力学習の難しさから、「こなすだけ」で終わり、定着しないケースが起こりやすい
- 攻略の基本は、Level Aで基礎 → Level Bで標準~応用を徹底反復 → 必要に応じてLevel Cへという段階的学習
- 分からない問題をそのままにせず、理解 → 練習 → 反復のサイクルを回す「仕組み作り」が重要
- エスコットでは、板書プリント・データ管理・学年別コース・オンライン授業を組み合わせ、体系数学を「負担」から「武器」へと変えるサポートを行っています
体系数学は難しく感じることもありますが、取り組み方を整えることで、学力の土台になりやすい教材でもあります。
学校の進度と本人の理解度に合わせて、無理のない計画で進めていきましょう。


